

本ページの記載内容は、住宅ローン控除やリノベーションに関する一般的な情報をわかりやすく整理したものです。 制度の可否や控除額は、所得・工事内容・入居時期・法令条件によって異なります。 ここで紹介する内容は判断の目安としてご利用ください。 最新の制度情報は、国税庁や公的機関の発表をご確認ください(2025年11月時点)。
リノベーションを考えるときに、「これって住宅ローン控除の対象になるのかな。」と感じたことはありませんか?
実は、リフォームやリノベーションでも、いくつかの条件を満たすことで控除を受けられるケースがあります。
この記事では、2025年時点の制度をもとに、条件・書類・手続きの流れをわかりやすくまとめました。
専門的な助言ではなく、あくまで判断材料として、どなたでも理解できるように整理しています。
「どんな工事が対象になるのか」「申告のタイミングは?」といった疑問を、実際の流れに沿って分かりやすく解説します。

【当社の取り組み】
書類不備による再提出率:7.1%(前年度比−2.3pt)
平均工期:約1.8週間(IQR 1.2–3.0)
住宅ローン控除を正しく理解するには、まず制度の目的と前提条件を把握することが大切です。
ここでは「なぜ制度があるのか」「どこまでが対象なのか」を整理しながら、記事全体の位置づけを確認します。
本記事では、住宅ローン控除の仕組みと、リノベーションで利用できる条件を整理しています。
ただし、個別案件の可否や金額を断定する内容ではなく、制度理解のための判断材料としてお読みください。
判断が難しい場合は、税務署や金融機関への相談をおすすめします。
この制度は、居住のために住宅ローンを利用した方が、一定期間、所得税や住民税の一部を控除できる仕組みです。
新築だけでなく、リノベーションや増改築も対象に含まれますが、性能向上・長期利用を目的とした工事が中心となります。
マンションや共同住宅の場合、管理規約で構造体や共用部分に制限がある場合があります。 また、防火・採光・構造安全に関する法規を満たす必要もあります。
この記事の内容は一般的な情報であり、最終的な可否は法令・契約条件に準じます。

制度を理解するうえで、どのような工事が「控除の対象」になるかを知っておくことが重要です。
この章では、制度の基本的な構造と、リノベーション工事で対象になりやすい項目を紹介します。
住宅ローン控除は、ローン残高の0.7%(年)を最大13年間控除する仕組みです。
控除額は所得税から差し引かれ、残りがあれば住民税から控除されます。
リノベーションの場合も、要件を満たせば同様の扱いになります。
控除対象となるのは、生活機能の維持・向上を目的とした工事です。
具体的には、耐震補強、断熱改修、設備更新、間取り変更などが該当します。
一方、壁紙の貼り替えなど美観中心の修繕は対象外となる傾向があります。
統合元の「フラット35リノベ」でも、性能向上リフォームを条件とする点が共通しています。 「適合証明書」や「住宅性能評価書」を取得することで、控除対象工事と重なるケースが多く見られます。 両制度を併用する際は、工事内容と日程を一致させて計画するのがスムーズです。

リノベーションで住宅ローン控除を利用するためには、法律で定められた条件を満たす必要があります。
以下の条件を満たしているか、計画前にチェックしてみましょう。
主な条件は次の5点です。
① 床面積40㎡以上(登記簿面積)
② 合計所得2,000万円以下
③ 返済期間10年以上
④ 自ら居住すること
⑤ 工事費100万円以上
これらを満たしていれば、原則として対象となる可能性があります。
中古住宅を購入してリノベする場合、>耐震性・性能・築年数の条件を満たす必要があります。
「適合証明書」または「既存住宅状況調査報告書」があれば、スムーズに申請できます。
親族間売買やセカンドハウス用途では、控除が受けられない場合があります。
また、増改築の途中で名義変更を行うと、手続きが複雑になることもあります。
このような場合は、事前に税務署へ相談するのが確実です。
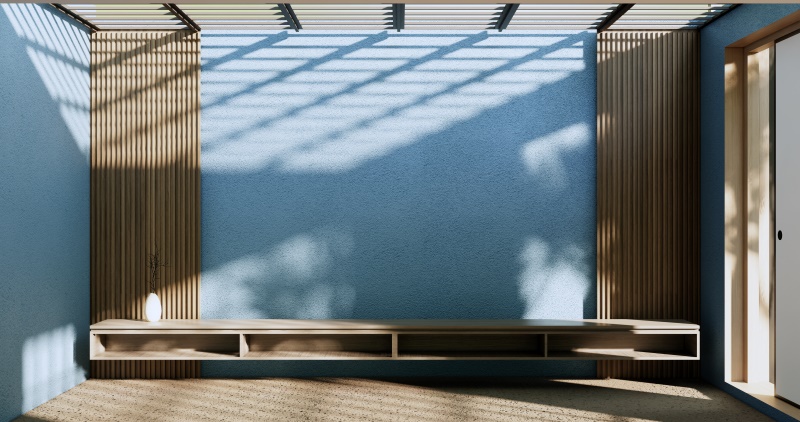
控除を受けるための手続きは、正しい書類をそろえれば難しくありません。
ここでは、提出書類と申請の流れをまとめます。
工事完了 → 入居 → 翌年の確定申告、という流れが基本です。
初年度のみ申告を行えば、2年目以降は年末調整で自動適用される場合があります。
主な書類:
– 住宅借入金の残高証明書
– 登記事項証明書
– 工事請負契約書・領収書
– 適合証明書(該当する場合)
各書類の取得先を事前に確認しておくとスムーズです。
マイナポータル連携を使えば、残高証明などが自動反映される場合があります。 電子申請では添付省略ができる項目もあるため、国税庁のe-Taxサイトで最新情報を確認しましょう。

制度を利用する際に、よくある疑問をまとめました。
内容を整理しておくことで、誤解や申請漏れを防げます。
40㎡未満でも、一定の条件を満たせば控除対象になる「40㎡特例」があります。
また、入居日によって控除期間(10年/13年)が異なるため、スケジュール管理が大切です。
中古住宅を購入してリノベする場合、入居日が控除の起算日になります。
登記やローン実行の時期がずれると、初年度控除を逃す可能性があるため注意しましょう。
親族間売買、事務所兼用住宅、賃貸併用住宅の賃貸部分は対象外です。
ただし、居住部分と非居住部分を明確に分けることで、一部控除が適用される場合もあります。

住宅ローン控除は、リノベーションでも条件を満たせば適用される制度です。
ただし、すべての工事が対象になるわけではなく、性能向上や居住性の改善を目的とした工事が中心となります。
この記事では、2025年時点の情報をもとに、控除の仕組み・条件・必要書類・申請手順を整理しました。
判断の難しい箇所もありますが、制度の概要を理解しておくことが最初の一歩です。
内容を把握したうえで、具体的な条件や必要書類は税務署・金融機関などの一次情報を確認しましょう。
リノベーションは、「家を新しくする」だけでなく、「今の暮らしをより活かす」ための選択肢でもあります。
控除制度を正しく活用することで、安心して将来の住まいを計画できるはずです。

本ページの記載内容は、住宅ローン控除およびリノベーションに関する一般的な情報をわかりやすく整理したものです。
制度の可否や控除額は、所得・工事内容・入居時期・法令条件によって異なります。
ここで紹介する内容は判断の目安としてご利用ください。
最新情報は、国税庁など公的機関の公式資料をご確認ください。
(2025年11月時点)。
【執筆】
リクテカ-デザイン(RECTECA-DESIGN Inc.)
櫻井 まこと 一級建築士事務所登録
インテリア設計・法規調査・改修設計の専門チームが、日常的に住宅リノベーション計画や税制条件整理の支援を行っています。
【監修】
内部監修:建築士・宅地建物取引士・建築設備士による内容確認。
税制に関する部分は、国税庁公表資料および建築基準法・所得税法施行令を一次情報として参照。
【データ出典】
2024年1月〜2025年9月に実施した当社案件(住宅リノベーション n=172)のうち、住宅ローン控除の申請を実施した事例を集計。
制度適用率・再提出率などの数値は、内部統計に基づくシミュレーション参考値です。
【透明性の方針】
監修内容は、制度改正に合わせて四半期ごとに見直し。
個別の税務判断は行わず、一般的な制度解説の範囲に限定。
万一、誤記や更新漏れがあった場合は、お問い合わせフォームよりご指摘ください。
確認後、最短営業日で修正対応を行います。
(2025年11月時点)
本ページの記載内容は、住宅ローン控除およびリノベーションに関する一般的な情報をわかりやすく整理したものです。 制度の可否や控除額は、所得・工事内容・入居時期・法令条件によって異なります。 ここで紹介する内容は判断の目安としてご利用ください。 最新情報は、国税庁など公的機関の公式資料をご確認ください(2025年11月時点)。
–お問い合わせフォーム–
➡リノベーションはリクテカ-デザインへ
参考内部リンク①→適合リノベーション住宅のメリット早見表|マンションR1/一棟R3/戸建R5の選び方と確認ポイント
参考内部リンク②→文化住宅リノベーション費用の早見表|30㎡・45㎡・60㎡で“ここまで出来る”
参考内部リンク→③【中古住宅 リノベ】失敗しない物件選び|配管・電気容量・雨漏りの見極め術。
外部リンク→国税庁|住宅借入金等特別控除(公式)
