

「オフィスがうるさい」「照明がまぶしい」——そんな声を聞いたことはありませんか?
実はそれ、感覚過敏によるストレスが原因かもしれません。
本記事では、音・光・匂いなどの感覚刺激を抑えたオフィス設計について解説します。
ニューロダイバージェント(神経多様性)に配慮した空間づくりは、すべての社員の働きやすさにもつながります。
快適で集中できる職場環境づくりのヒントを、ぜひご覧ください。
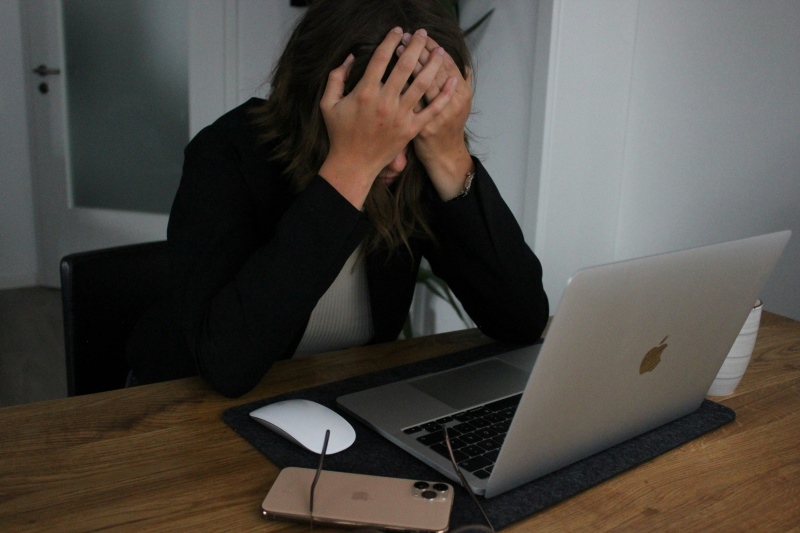
現代のオフィスでは、音・光・匂いなど、さまざまな刺激が無意識のうちに社員の集中力を奪っています。
特に、感覚過敏や発達特性を持つニューロダイバージェントの社員にとっては、その刺激がストレスの原因となり、働きづらさにつながることもあります。
快適な職場づくりの第一歩は、こうした見えにくい問題に気づくことから始まります。
感覚過敏とは、音・光・匂い・触感などの刺激に対して、通常よりも強く反応してしまう特性のことを指します。
特に発達障害のある方に多く見られますが、健常者でも疲労やストレスで一時的に敏感になる場合もあります。
「照明がまぶしくて目が痛い」「周囲の音で集中できない」といった声は、そのサインかもしれません。
本人も原因がわからず苦しんでいるケースも多く、配慮のある環境づくりが求められています。
私たちの脳は、周囲の刺激に常に反応しています。
音や光が多すぎると、情報処理の負荷が増え、脳が疲弊して集中力が続かなくなってしまうのです。
感覚過敏のある方にとっては、その影響が特に大きく、作業パフォーマンスやメンタルにも直結します。
働く環境から余分な刺激を取り除くことで、脳のリソースを業務に集中できるようにする設計が重要です。
社員の働きやすさには、「空間設計」「音環境」「照明」「温度湿度」などの物理的要因が大きく関わっています。
これらが適切でないと、気づかないうちにストレスが蓄積し、生産性の低下や離職につながることもあります。
特に、年齢、性別、能力、文化などの違いに関わらず、できるだけ多くの人が利用しやすい「ユニバーサルな空間設計」が、これからのオフィスに求められています。
感覚過敏の方に優しい環境は、結果として全社員のパフォーマンス向上にもつながるのです。

「音」は、オフィスで最も見落とされやすいストレス源のひとつです。
電話のベル、会話、複合機の動作音、空調のノイズ……。
こうした音の積み重ねが、集中力を削ぎ、イライラや疲労の原因となることがあります。
ここでは、音のストレスを軽減するための設計上の工夫を解説します。
まず効果的なのは、吸音性の高い素材を活用することです。
たとえば、布張りの間仕切り、吸音パネル、カーペット、アコースティックパネルなどを取り入れることで、音の反響を抑えて空間全体の静けさを確保できます。
特に天井や壁、デスク周辺に吸音材を取り入れることで、耳に残る不快な残響を軽減できます。
簡易設置が可能なパネルも多く、リフォームなしでも導入可能な手軽さも魅力です。
オフィスの中で音の発生源となりやすい場所には、集音や遮音の対策が必要です。
たとえば、複合機は専用スペースに設け、ドア付きの収納エリアに設置するといった工夫で動作音を抑えられます。
また、会話が多く発生するエリアと集中作業エリアを分けてゾーニングすることで、音の干渉を防げます。
空調設備の音が気になる場合は、静音設計の機器を選ぶこともポイントです。
オフィス内に「静音重視の集中スペース」を設けることで、感覚過敏のある社員や集中したい社員の選択肢を広げることができます。
このようなスペースでは、吸音材に加えて音楽やアロマを排除し、極力シンプルな環境にするのが理想です。
また、使用のルールやサイン表示を明確にすることで、周囲の理解と協力も得られやすくなります。
音のない空間は、一部の人にとっては「思考が深まる特別な場所」となり、生産性向上に大きく貢献します。

「まぶしい」「チカチカする」「色がうるさくて落ち着かない」――これらの感覚は、視覚過敏の方が日常的に感じるストレスです。
視覚刺激を抑える工夫は、目の疲れや集中力低下を防ぐだけでなく、全体の快適性を高める効果もあります。
ここでは、照明や色彩における配慮のポイントを解説します。
感覚過敏の方にとって、強すぎる蛍光灯や色温度の高い照明はストレスの原因になります。
そのため、オフィス照明では、**「調光機能付き」「間接照明」「色温度4000K前後の中間色」**など、目に優しい仕様を選びましょう。
また、ディスプレイの光と天井照明のバランスも大切で、反射や逆光にならないような配置にも配慮が必要です。
自然光との調和を意識することで、視覚的な疲労を大幅に軽減できます。
内装や家具の色は、刺激の少ない自然なトーンを基本にすることが重要です。
具体的には、ベージュ、グレー、グリーン、アースカラーなど、落ち着いた色合いが好まれます。
カラフルすぎる空間は視覚情報が多くなり、脳が疲れやすくなるため注意が必要です。
また、**エリアごとに色の役割を明確にする(集中エリアは寒色、リラックスエリアは暖色)**ことで、空間の意図を感覚的に伝えることもできます。
照明を固定せず、**時間帯や用途に応じて調整できる「可変照明」**を導入すると、感覚過敏の方にも柔軟に対応できます。
たとえば、朝は明るく、午後は落ち着いた色温度にするといった使い分けが可能です。
また、自然光を取り入れやすい配置にすることで、人工照明の負担を軽減する効果もあります。
ただし、直射日光は逆効果になることもあるため、ブラインドやすりガラスで調整できる設計が理想です。

「オフィスの匂いが気になる」「空気がこもっていて息苦しい」――こうした感覚は、感覚過敏の人にとって強いストレスになります。
匂いや空気感は目に見えにくいものの、五感の中でも感情や集中力に深く関わる要素です。
快適な職場環境を整えるには、こうした**“空気の質”への配慮**も欠かせません。
まず意識したいのが、強い香りを持つものの使用を最小限にすることです。
たとえば、芳香剤・アロマ・消臭スプレー・食べ物の匂いなどは、感覚過敏の人には耐えがたい刺激となることがあります。
また、**ビニールや塗料、カーペットの新素材などが発する“化学的な匂い”**も、体調不良の原因になることがあります。
匂いの強いアイテムは、専用スペースを分ける、換気設備を強化するなど、使い方に工夫を取り入れましょう。
空気中のホコリや微粒子も、感覚過敏の人には刺激となります。
そこでおすすめなのが、空気清浄機の設置や、観葉植物による自然な空気浄化効果の活用です。
植物は見た目のリラックス効果だけでなく、二酸化炭素の吸収や湿度調整にも貢献します。
また、化学物質を吸着するタイプの空気清浄機を使えば、体に優しい空間づくりが可能になります。
空気感には、「匂い」だけでなく、温度と湿度も大きく関係しています。
冷暖房の効きすぎや乾燥は、肌や喉の刺激となり、不快感や体調不良の原因になりやすいのです。
そのため、温湿度計の設置や加湿器・サーキュレーターの導入で、空気環境を数値で把握・調整することが重要です。
特に、個別に調整できる機器を使うことで、多様な快適性ニーズに対応できます。

感覚過敏に配慮したオフィス設計は、単なる「福祉」や「優しさ」の枠を超え、企業の競争力そのものに直結する戦略的施策です。
すべての社員が快適に、集中して働ける空間を提供することは、長期的な成果として企業にも大きなメリットをもたらします。
静かで落ち着いた空間、まぶしすぎない照明、空気が澄んだオフィス――。
これは決して特定の人だけのための環境ではありません。
実は、こうした空間は感覚過敏がない社員にとっても、集中力・快適性を高める要因になります。
つまり、ニューロダイバージェント対応は「誰にとっても働きやすいオフィス」をつくる第一歩といえます。
働く環境に不快感やストレスがあると、「続けられない」「能力を発揮できない」と感じる社員が離職する可能性が高くなります。
一方で、感覚への配慮があるオフィスでは、社員のエンゲージメントが高まり、会社への信頼感も育まれやすくなります。
これは特に、採用・育成コストの軽減や定着率の向上といった面で、企業にとって大きな利益となるでしょう。
多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包括性(Inclusion)への取り組みは、いまやグローバル企業だけの課題ではありません。
中小企業においても、社員の個性を尊重し、全員が能力を発揮できる環境づくりが求められています。
感覚過敏や発達特性への理解を深めたオフィス設計は、外部からの企業評価やブランディングにもプラスに働く要素です。
今後ますます、こうした視点を持つ企業が社会から選ばれていくのかもしれませんね。
感覚過敏やニューロダイバージェントに配慮したオフィス設計は、働く人すべてにやさしい環境づくりにつながります。
音・光・匂い・温湿度といった感覚的な要素を丁寧に見直すことで、社員の集中力や働きがいを高める空間を実現できます。
こうした配慮は単なる「特別扱い」ではなく、離職率の低下や企業イメージの向上といった実質的なメリットにも直結します。
ぜひ、オフィスの内装設計を見直す際には、感覚刺激を抑えた空間づくりという視点を取り入れてみてください。
